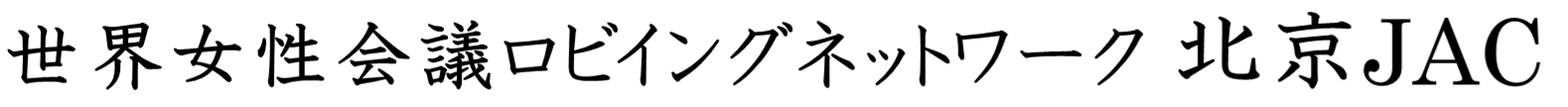第三号被保険者制度を廃止し、短時間労働者の社会保険加入要件の企業規模の全廃を
各位2025年5月
北京JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク)わくわくシニアシングルズ
平素より国政・地方行政にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。私たちは女性の人権・差別・貧困問題に取り組んでいる団体です。厚生労働省が5月16日年金制度改正法案を国会に提出した事を受け、「第三号被保険者制度を廃止し、短時間労働者の社会保険加入要件の企業規模撤廃を迅速に行う」ことを要望します。1986年、国民皆保険のもと会社員(第2号被保険者)の配偶者で年収130万未満であれば、国民年金保険料を払うことなく満額の基礎年金を受給できる第三号被保険者制度(対象者98%が女性)が発足して40年になろうとしています。発足当時は専業主婦世帯が大半を占めていましたが、2023年の世帯数(総務省「労働力調査」)によると、共働き世帯が専業主婦世帯の約2.5倍、専業主婦世帯は少数になっています。また配偶者のいない未婚・離婚の女性も増加。本制度は夫が仕事、妻が家事育児、家計補助で働く性別役割分担家族を想定していますが、家族の形態の時代の変化に対応できていません。また本制度が年収の壁をつくり、その結果、税や社会保険料の支払いを忌避する主婦パートの働き控えを生み、そのことで女性の低賃金化をもたらし、男女の賃金格差是正を遅らせている要因の一つになっています。このことは経済界や労働組合など各方面から指摘されていることです。今国会での年金改正では、厚労省が関連法案の附則に初めて第3号被保険者制度の在り様の検討規定を設けたと聞き及んでいます。女性を被扶養者として位置づけるのではなく、ひとりの人間として生きていくことのできる「真っ当に働く権利」を保障する視点から、女性の就労を阻害せず、働き方に中立な年金制度改革を望み、第3号被保険者制度の議論が活発に行われることを切に要望します。
―3号被保険者制度廃止の理由―
1.第三号被保険者制度は、配偶者の有無や配偶者が加入している保険で国民年金保険料納付を決める不公平な制度である
1986年の国民皆年金施行に伴い、20歳以上60歳未満の配偶者のいる妻(夫)も国民年金の第三号被保険者として包摂され年金権が樹立されました。しかしこの制度は保険料の支払いは求めず、厚生年金加入者の保険料と会社負担分で肩代わりするという、社会保険の原則をも逸脱したものであり、女性の社会進出、人々の意識の変化に伴い、制度自体が多様な女性のライフスタイルに非中立的、不公平な制度であることが明らかになってきています。女性が諸事情により退職した場合、会社員の夫がいる妻は第3号被保険者になれるが、夫自営業の妻やシングルマザー・シングル女性は1号被保険者です。これは、配偶者の有無や夫の加入年金により、女性の年金のあり方が決まるという、女性にとって差別的であり公平・中立の制度とは言えません。3号被保険者の割合は夫の所得が1千万以上になるとその割合が高くなります(厚労省の年金部会の資料)。非正規雇用・低賃金で働く女性が、高所得の夫がいる妻の年金を支える「いびつ」な構造を引き起こしています。このような「いびつな」で女性差別を再生産する第3号保険制度は日本の性差別を解消するためにも見なおし、廃止する方向で検討することを要望します。3号制度とともに130万未満の収入であれば介護・医療保険料を免除される現行の医療保険被扶養者の規定の縮小検討を要望します。日本の社会保障制度にとって大切なのは誰もが所得に応じて保険料を払い社会を支える仕組みを作ることだと考えます。
2.第三号被保険者制度は就労の壁をつくり、女性の低賃金化を誘導し経済的自立を阻む制度です。
3号主婦パートの女性が夫の扶養内に留まるために、あえて労働時間や収入を抑えるいわゆる働き控えが足下の人手不足もあり社会問題化しています。主婦パートが年収の壁として意識する収入ライン106万は、厚労省の改正案で撤廃の方向ですが、今後は週20時間が壁になることが想定されます。第3号制度や健康保険の被扶養制度がある限り、壁は無くなりません。実際2022年従業員101人以上に厚生年金が適用された際、1号被保険者の77%が加入、3号被保険者の48%が回避しました(厚労省年金部会の資料より)。
女性は年齢が高くなると非正規雇用しか選択肢がなくなる人も多いため、扶養枠におさまりたい3号主婦パートの就労調整は、シングルや共稼ぎ非正規女性の賃金にも影響します。同じ土俵で働くために、3号以外の女性の賃金上昇を阻み、「女性の賃金は安くていい」という誤った認識を社会に醸成させ、引いては男女の賃金格差の是正の動きを遅らせていると言えます。ジェンダー平等社会は女性の経済的自立を伴う社会。そのためにも女性の経済的自立を阻む3号、夫の扶養下に置こうとする3号制度は廃止すべきです。
―現役・高齢期の女性が貧困に陥らないために―
短時間労働者の社会保険加入要件の企業規模撤廃を速やかに撤廃すること。
高齢期単身女性の貧困率は44,1%。これは現役母子家庭とほぼ同じ高い貧困率。働いても厚生年金に加入できず低額な国民年金のみの加入であったことや、女性の低賃金が背景にあります。高齢期に女性が貧困に陥らない、働く現役女性が貧困化しないためにも最低賃金の引き上げとともに、働いていれば厚生年金に加入できるように制度改正を行うことが必要であり、短時間労働者の社会保険加入は今回の年金改正の重要なテーマです。厚生労働省も、保険料の担い手を増やし制度の持続可能性の確保のため、短時間労働者の厚生年金加入を促進し、週20時間以上の労働(対象となる企業規模は従業員50人超)で収入要件106万も撤廃の方向。本年始め、厚労省は2029年10月に10人以下の企業も対象になる案を出していたが、改正案によると企業規模全廃は2035年10月からです。10年後全廃では余りにも遅すぎます。女性の経済的貧困が置き去りにされかねません。早急に週20時間就労で誰もが厚生年金に加入できるように企業規模要件を速やかに撤廃することを要望します。
- 国連女性差別撤廃委員会への拠出停止の撤回を求めます 2025年2月
2025年2月10日
外務大臣 岩屋 毅 様
国連女性差別撤廃委員会への拠出停止の撤回を求めます
1月29日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、対日審査最終見解において、皇室典範改正を勧告したことに対する措置として、同委員会を日本の拠出金の使途から除外することを国連側に伝えたとの報道がなされました。
皇室に関する事柄は、普遍的人権の対象外であり、CEDAWが触れるべきではないという政府の主張は、日本国内においてしか通用しないものです。今回の政府見解は、性差別撤廃に向けた国際基準との大きな乖離を示しています。
女性差別撤廃条約2条は、性差別となる国内法の改正を求めています。「男系男子」の皇位継承を定めた皇室典範は、明らかに性差別であり、改正の勧告は、批准国として受け入れ検討するのは義務だと考えます。
今年は、国連主催の第4回世界女性会議が北京で開催されてから30年目を迎えます。3月にはニューヨークで第69回国連女性の地位委員会主催の国際会議が開催され、「北京+30」をテーマに各国政府が30年間のレビューを報告することになっています。
このような女性の人権にとっての重要な年に、日本政府の今回の決定は極めて遺憾であり、即撤回を求めます。また条約批准国として、勧告を速やかに実施することを求めます。
私たちは、北京世界女性会議以降、『北京行動綱領』の日本国内での実現に向けて30年間、活動を続けてきました。
ご周知のように、「北京行動綱領」は、性差別をなくし、女性の基本的人権を確立することが環境、開発、人口、平和などの解決には不可欠であることを明記した包括的国際文書であり、政府が取り込むべき行動指針です。
これは、日本の女性たちを含めたNGO、市民社会が策定に関わり誕生したものです。
しかし、この行動指針への、日本政府の取り組みが、30年間、決して十分ではなかったことは、ジェンダーギャップ指数が示しています。
今回の決定に対しする説明責任を果たすためにも、今後、CEDAWの勧告及び「北京行動綱領」を実施し、性差別解消を進めるために、市民社会との開かれた対話の場を設定することも強く要望します
北京JAC(世界女性会議ロビイングネットワーク)